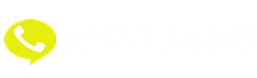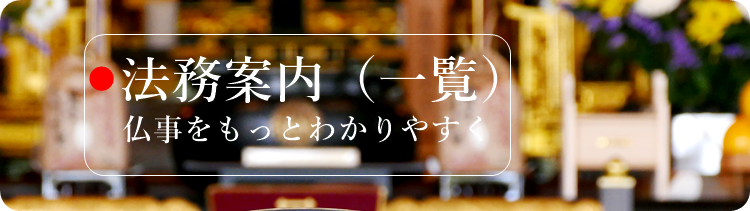住職法話
2026.01.01
新しい年を迎えて‐縁起と心の力

昨年は世界情勢や政治・経済の世界が色々と動いた年だったように感じます。昨年1月に第二期のトランプ政権が誕生したこともあり、どうなるのかなと不安をもって年を始めた方も多かったと思います。それから日本も女性初の総理が誕生し、身近なところだとお米の値上がりや熊被害など色々とありましたが、何とかこうして新しい年を皆様と迎えることができました。今年は午年、それも「丙午」(ひのえうま)の年に当たります。昔からある暦は基本的に十干と十二支の組み合わせ(60通り)で回っておりますので、60歳の方は「還暦」と呼ばれます。
その中で、有名な組み合わせとして、60年の一番目である「甲子」(きのえね)は縁起が良いとされて有名です。かの高校野球の聖地、甲子園も元々はここから名づけられています。そんな「甲子」と並んで暦の中で有名なのがこの「丙午」です。この丙午は何が有名かというと十干十二支の中でそれぞれ「火」の意味を含む「丙」と「午」が重なることによって火災などが多い年と言われました。そこから浄瑠璃などの作品と結びついて気性の激しい女性が生まれる、という迷信が日本で広まり、前回の丙午である1966年の際には25%も出生率が下がったという印象深い年です。もっとも、1966年生まれは子どもの人数が少なかったこともあり、就職などの際には競争率が下がった当たり年とも後に言われましたのでまさに迷信だったのでしょう。言葉が伝わっていくなかで意味が変わってしまうというのはよくあることだと思います。
昨年の話にはなりますが、NHKの番組「チコちゃんに叱られる!」では「貴様」「ご苦労様」という言葉が取り上げられていました。現代では「貴様」は悪口になりますし、「ご苦労様」は目上の者が目下に使う言葉とされています。単純に文字として見ると、「貴(とうと)い」「あなた様」、また「人様の苦を労(ねぎら)う」ですから、どちらも悪い意味ではありません。ではどうして現代では使い方に注意をしなくてはいけないのか、というテーマでした。私も分からなかったのですが、テレビで挙げた理由としては「敬語は時間が経つと敬意がすり減っていくから」というものでした。
例えば昔、「貴様」という言葉は一部の特権階級の方だけに使っていたそうです。しかし、時代を経ると徐々にその階級の方とも交流がある商人や僧侶が他の一般の方に敬意を示す形で使い始めたそうです。そして世間一般の方にも定着した敬語は、逆に一部の特権階級の方からすると「一般人と同じ敬称」ということで敬意がすり減り、悪口として扱われるようになったそうです。「ご苦労様」も同様で徐々に使い方が変わったそうです。丙午のような迷信とは違いますが、使い方や時代によってイメージが徐々に悪くなってしまったこと、そしてその変化は特権階級や大衆などの人々、捉え方や使い方など「いくつもの要因によって起きた」ということを示す良い例だと思います。
仏教からも一例として「出世」という言葉を紹介したいと思います。「出世」という言葉は今でこそ職場での昇進、出世競争など、どちらかというと俗っぽい言葉として使われますが、漢字としては「世に出る」と書きます。仏教用語としては元々「お釈迦様が仏の世界ではなく、人の世界に出て我々と同じ人の身として教えを説き、自分だけでなく万人を悟りに導くこと」を指します。それが徐々に職場において「新しい立場になって同僚や後輩を指導すること」に通じるからこそ、「出世=昇進」という言葉になっていったのだと思います。現代では「苦労や責任ばかりが増えるから出世をしたがらない」と聞きますが、本来の仏教的な意味も含めて考えると、自分のことで精一杯な現代において、周囲を良くしたいという強い想いが無ければ出世をしたがらないというのはまさに原点回帰、本来の意味合いだと思います。こうやって仏教の教えも含めて考えると「出世」に対する俗っぽいイメージが少し良くなりませんか。
ここまでの事例で伝えたかったことは「言葉や物事に対するイメージ」は①様々な要因で成り立っていること。②その中の一つとして自分の考え方や捉え方など、自分の心も要因、ということです。仏教では全ての物は単独で存在せず、「縁起(いくつもの原因・要因・縁など)」によって存在しているという考え方をします。だからこそ、自分の心を一つの縁起として物事のイメージを変化させることができるのです。これは重要な「心の力」だと思っています。
年齢を重ねた方ほど、この変化の激しい時代に聞きなれない言葉や見慣れない光景に出会ったことはないでしょうか。そしてそれらがドンドンと増えていませんか。私はそれらを自分とは繋がりの薄いもの、縁遠いものとして捉えてしまうのは「悪い縁起」になると思っています。自分の周囲が見慣れない物ばかりになってしまった時、皆さんは居心地の悪さを感じませんか?昔に比べて現代ではインターネットやAIなどにより益々変化が早まり、これからも様々な言葉や光景が出てくるでしょう。それに翻弄されるだけではドンドンと流され、迷い、不安を抱えながら生きる形になっていくと思っています。だからこそ、大事なことは「良い縁起」を結ぶ為の「心の力」だと思っています。聞き慣れない言葉や見慣れない光景があった時、それらはどういう原因・要因で出てきたか、そして皆様とどう繋がるのかを考えていくことが大切です。辿っていけば「無から有は生まれない」という言葉もあるように、必ず皆様に身近な出来事や気持ちと繋がり、「縁遠かったもの」が「身近なもの」に変わっていくと思うのです。繋げ方は人それぞれです。最初に出てきた丙午もその根底にある「生まれる我が子が良い子であって欲しい」という親御さんの想いまで考えると心ある優しい年に思えますし、昨年に言われた「令和7年は丁度、昭和100年」という数え方は、まさに昭和と令和を繋ぐ良い縁起だと思います。ぜひ皆様も昭和101年である令和8年、その初めのお正月に「心の力」で良い縁起を結び、身近なものに囲まれた安心できる年を目指してみてはいかがでしょうか。
back number
▶2025年 住職法話一覧
![]()
2025.08.13
●「アンパンマン」/やなせ たかし さんを偲び
2025.06.01鬼子母神大祭法話
●身口意を一致させ、良くしましょう
2025.03.20
●西田敏行さんを偲んで(六波羅蜜の先に)
2025.01.01 新年法話
●新しい年を迎えて必要なものごちゃまぜ
![]()
2024.08.15 お盆法話
●父の33回忌にあたり
2024.06.02 鬼子母神大祭
●智慧 (後半) 仏知見(ぶっちけん)
2024.03.20 彼岸
●智慧(前半)人の物事の見方
2024.01.01 新年
●コロナ後の新年を迎える―少欲知足
![]()
2023.08.14 お盆法話
●「川の流れのように」/美空ひばりさんを偲び
2023.06.04 鬼子母神大祭法話
●「祈ってください」とChatGPTにお願いしてみた
2023.03.21 彼岸法話
●禅定 心の安定
2023.01.01 新年
●新年を迎えるにあたり 心を前に動かす
![]()
2022.08.13 お盆
●安倍晋三元総理のご冥福を願い
2022.03.21 春彼岸
●ウクライナ問題、収束を願い
2022.01.01 新年
●コロナから前に進む
![]()
2021.06.12 鬼子母神祭
●幸せの素人
2021.03.19 春彼岸
●六波羅蜜の「精進」について
2021.01.01 新年
●暦とは何か(年月日のお話)
![]()
2020.12.02 年末
●人形供養に関して
2020.08.23 お盆
●葬儀の説明(変えるもの、変えぬもの)
2020.06.08 鬼子母神大祭
●灯(ともしび)について
2020.03.18 春彼岸
●六波羅蜜の「忍辱」について
2020.01.01 新年
●中村 哲(なかむら てつ)医師を偲んで
![]()
2019.06.01 鬼子母神大祭
●川崎市の児童殺傷事件を受けて
2019.03.19 春彼岸
●六波羅蜜の「持戒」について
2019.01.01 新年
●平成の終わりに際して
![]()
2018.05.01
●通夜・葬儀・49日・回忌法要
2018.0501 鬼子母神大祭
●四諦(したい)八正道(はっしょうどう)
2018.03.18 春彼岸
●六波羅蜜の「布施」について
2018.01.01 新年
●新年を迎えて
![]()
2017.08.08 お盆
●盆施餓鬼供養の説明
2017.06.05
●御首題・御朱印の説明
2017.05.01 鬼子母神大祭
●御札・御祈祷の法話
2017.03.18 春彼岸
●仏道修行